ワインを飲むとき、グラスを軽く回して香りを楽しむ「スワリング」。
実は、このスワリングの回す方向によってワインの香りや味が変わるという説があるのをご存じですか?
 ナナシー
ナナシー右回し・左回しで本当に違いが出るの?
科学的な根拠は?



どちらの回し方が正しいの?
このような疑問を持つ方に向けて本記事ではワインのスワリングと風味の関係をリサーチしました!
≪読むとわかる3つのこと≫
・ワインの右回し・左回しによる違い
・科学的な根拠や専門家の見解
・正しいスワリング方法で香りを最大限に楽しめる
「なんとなくワイングラスを回していたけど、ちゃんとした理由があるの?」と感じた方。
この記事を読めばワインのスワリングに関する知識が深まり、より美味しくワインを味わうことができます。
美味しいワインをお探しの方はこちらが必見です!




ワインの右回し・左回しで香りや味は変わるのか?
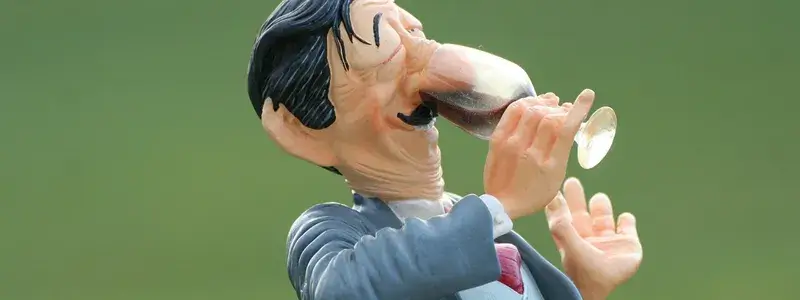
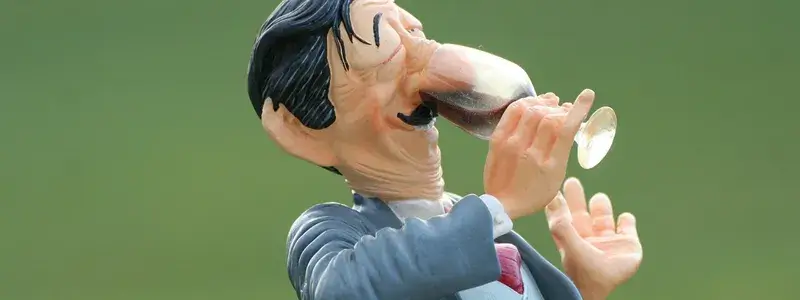
結論から申し上げますと、多くの議論は交わされていますが明確な答えはありません。
ただ、否定しきれない事実はいくつか存在しており、その証明にまで至らないのが実情です。
まずは「スワリング」をする理由を再確認してみましょう。
そのうえで、ワイングラスの右回し・左回しでワインの香りや味が変わるのではないかという議論があります。
【右回し(時計回り)】
⇒空気との接触が穏やかになり、ワインの香りがやさしく広がる
【左回し(反時計回り)】
⇒空気との接触が活発になり、香りの立ち方が強くなる
この違いの背景には、後ほど詳しく解説する「コリオリの力」や「空気の流れ」が関係していると言われています。
しかし、これらの効果にはまだ科学的な結論が出ていない部分も多く、議論の余地が残されている状態。
では、本当に回す方向で香りや味が変わるのか?
次にワインの回す方向と香りの関係について、科学的根拠をチェックします。
ワインの回す方向と香りの関係に科学的根拠はある?
ワインのスワリングの方向が香りや味に影響を与えるのか?
この疑問に対して一部の専門家や研究者が興味を持ち、科学的な視点から分析を行っています。
ワインの回す方向と香りの関係について、実際の研究や科学的根拠をリサーチした結果は次のとおりです。
【論文や科学的根拠の研究結果】
■ワインの回転と揮発成分の関係
ある論文では、ワイングラスを回すことでアルコールや香気成分の揮発速度が変化することが示されています。
しかし、右回し・左回しによる差については明確な結論は出ていません。
■空気の流れとワインの香り
ワイングラスの形状や回す方向によって、空気の流れが変化するという研究もあります。
この研究では、回転の方向が気流を変え、香りの拡散に影響を与える可能性があると示唆されています。
■人間の嗅覚と香りの認識の違い
別の研究では人間の嗅覚は個人差が大きく、回す方向よりも嗅ぐタイミングや環境の影響を強く受けるという結果が出ています。
これらの研究から「ワインの回転方向が香りに影響を与える可能性はあるが、明確な結論はまだない」ということです。
右回し・左回しについてワイン愛好家の意見は?



右回し・左回しは聞いたことがあるけど、正直違いはわからなかった。
でもスワリングで香りが立つのは確か。



右回しの方が香りがやさしく立ち上る気がする。
ただ、回す方向よりもグラスの形状やワインの種類の方が影響が大きいと思う。



試してみたけど、たしかに香りの立ち方が微妙に違う気がする…。
気のせいかもしれないけど(笑)
明確な結論はないものの、空気の流れや香りの拡散に何らかの影響を及ぼす可能性はあり、今後の研究が期待される分野。
どちらかと言えば「右回し・左回しの違い」よりも、適切なスワリングの仕方が大切というのが、多くの専門家の意見ですね。
コリオリの力とワイン風味の関係


ワインの右回し・左回しによって香りが変わるという説の中には「コリオリの力が影響を与えているのではないか?」という意見があります。
この「コリオリの力」とは何なのか、そして本当にワインのスワリングに影響を与えるのでしょうか?
【コリオリとは?】
”慣性系に対して回転する座標系内を運動する物体に作用する慣性力または見かけの力である。時計回りに回転する座標系では、この力は物体の進行方向の左側に働き、反時計回りでは力は右に働く。コリオリの力による物体の偏向はコリオリ効果と呼ばれる。コリオリの力を数学的に表現したのは、1835年にフランスの科学者ガスパール=ギュスターヴ・コリオリが水車の理論に関連して発表した論文が初出である。20世紀初頭、コリオリ力という言葉は気象学に関連して使われ始めた。”引用:wikiペディア
単純に言うとコリオリの力とは「地球が自転しているために生じる力のこと」です。
この力は、実際に次のような現象に影響を与えてます。
これらの影響を見ると、「ワインを回す方向にも関係があるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、多くの専門家らはコリオリの力がワイングラスのスワリングに影響を与えることはほぼないという意見が多いです。
なぜコリオリの力は影響しないの?
コリオリの力は、広い範囲で大きな質量が動くときに影響を与えるもの。
実際に上述したとおり台風や海流のように、数百キロメートル規模で動くものに強く作用します。
しかし、ワイングラスのスワリングは直径10cm程度の小さな円運動。
このサイズではコリオリの力の影響は極めて小さく、人間の手の動きの方が圧倒的に大きな影響を与えます。
そのため科学者の間では「ワインのスワリングにコリオリの力が影響を与えることはほぼない」と考えられています。
つまり、北半球だから右回しが有利、南半球だから左回しが有利ということはないでしょう。
ワインのスワリングに影響を与えるのは何か?
では、ワインの香りを引き出す上で本当に重要なのは何でしょうか?
それはコリオリの力ではなく、「スワリングの速度」「グラスの形状」「ワインの温度」がはるかに大きな影響を与えます。
ワインのスワリングにおいて、コリオリの力の影響は無いに等しいレベル。
北半球と南半球でスワリングの方向を変える必要はなく、ワインの種類やグラスの形状、スワリングの仕方の方が重要です。
そんな中、スワリングのテクニックを使わなくても誰もがワインを楽しめるようにと「香りに優れたグラス形状の設計手法」を研究した論文を見つけたので、要約してご紹介します。
香りに優れたグラスの形状設計手法
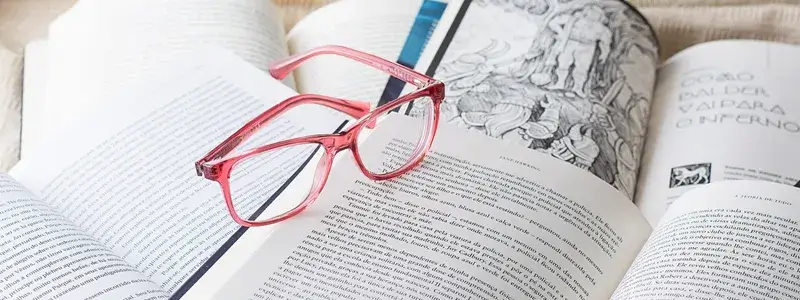
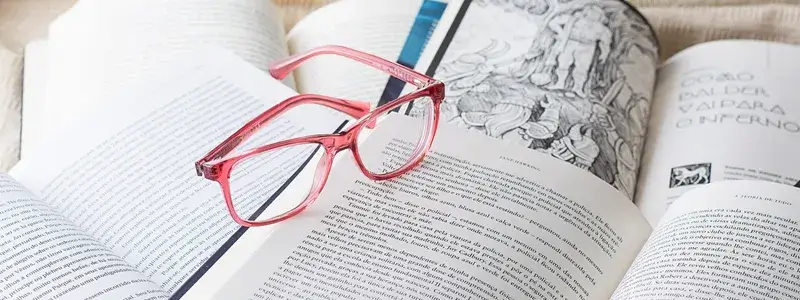
かみ砕くと、この論文には次のようなことが書いてあります。
つまり一言で表すと。
グラスの形が香りを決めるのは間違いなく、その最適な形を科学の力で設計できるようになったというものでした。
確かに現在は100均でも高いクオリティーのワイングラスは販売しています。
しかし、ワインの魅力を最大限に引き出すために、グラス選びはバカにできないということです。
ワイングラスは本格的なものでも1つあたり1,500円前後で入手できます。
ZWILLINGのワイングラス


また、以下の記事ではお祝いの品やハイクオリティーなグラスを紹介しています。
合わせてご拝読ください。


以降は、論文の内容を簡単にまとめたものです。
もしご関心があればご覧ください。
研究に至った背景について
香りはアルコール飲料の魅力の本質であり、香りを最大限に引き出すグラスは飲料の価値を高める重要な要素。
香りを引き立てるグラスの形状は経験的に知られており、多くの種類が市販されています。
しかし、これまで感覚に依存しており香りの拡散や残留を科学的に予測する手法は確立されていませんでした。
この問題を解決するため、本研究では「アルコールガスの可視化技術と Computer Aided Engineering(CAE)を組み合わせ、香りの挙動を模擬するCAEモデルを作成。
形状の異なるグラスの香りの強さを数値化し、ブレンダーによる評価と比較する。
実際の研究手法について
以下3つのグラス設計手法を開発。
・赤外線カメラによるアルコールガスの可視化
グラスにアルコール飲料を注ぎ、時間の経過とともに立ちのぼるガスを赤外線カメラで撮影。
これにより、普段は目に見えない香り成分(アルコールガス)の広がり方や滞留の様子を視覚的に確認。
グラスごとの形状の違いによって、香りがとどまるか逃げてしまうかが一目で分かるようになった。
・CAE によるグラス内空気拡散のモデル化
3D-CADでグラスをモデリングし、CAE(数値流体解析)を用いて内部の空気やアルコールガスの動きをシミュレーション。
これにより、実際の実験では確認しにくい細かな流れや濃度分布まで再現でき、グラス形状が香りに与える影響を数値化することが可能に。
・評価によるCAEモデルの検証
専門家やブレンダーによる官能評価を行い、実際に感じられる香りの強さとCAEシミュレーションの結果を比較。
その結果、香りが強いと感じられたグラスではCAEでも高濃度のガス滞留が見られるなど、両者の結果が良好に一致した。
これにより、開発したモデルの信頼性と再現性が確認された。
この研究の検証結果
赤外線カメラによる観察の結果、グラスの形状によって香りの滞留が大きく異なることが確認された。
特に赤ワイングラスでは、アルコールガスの一部がグラス内部に滞留し、香りが長く持続することが分かった。
一方、カクテルグラスなど開口部が広いグラスでは香りがすぐに拡散してしまい、香りの残留が少ないことが確認された。
香りが強いと評価されたグラスは、CAEモデルにおいても香りの残留が高い結果が得られた。
逆に、香りが弱いと評価されたグラスでは、CAEモデルでも香りの拡散が早いことが示された。
CAEモデルは識別できることが確認され、設計の精度向上が期待される。
本手法を用いることで、科学的に香りを引き出すグラスを設計することが可能になり、試作回数の削減につながる可能性が示された。
従来のように試作品を何度も作り直す必要がなく、数値解析によって香ため、効率的なグラス開発が可能になる。
この研究の結論
香りを最大限に引き出すグラスの形状を科学的に設計するための手法を開発 (数値流体解析)を組み合わせることで、香りの拡散を予測し、形状設計に活用できることを示した。
また、評価の結果とCAEシミュレーション結果の間に強い相関が確認されたことで、このモデルの有用性が実証された。
この手法を活用すれば、香りをより強く感じられるグラスを科学的に設計でき、製造プロセスの効率化が図れると考えられる。
今回はこちらの論文をご紹介しましたが、その他のより詳しい論文などは以下から閲覧できます。
なお、論文は全て英語で記されていますので、その点はご留意ください。
その他論文:GoogleScolar
ワインの香りを最大限に引き出す正しいスワリング方法
ワインのスワリングは香りを引き出し、味わいをより豊かにするための重要なプロセス。
前章で解説した通り、グラスの回転方向による影響よりもグラス種類や形状、スワリングの仕方が重要というのが結論です。
では、ワインの香りを最大限に引き出すにはどのようなスワリング方法がベストなのか?
ここでは正しいスワリングの方法をはじめとして、NGスワリング、そしてワインの種類別のコツを解説します。
【スワリングの基本ステップ】
1.ワイングラスを持つ
⇒グラスの「脚(ステム)」を持つことで手の熱でワインの温度が上がるのを防ぎ、香りのバランスを保つ。
2.グラスを小さく円を描くように動かす
⇒「ゆっくり、一定のスピード」で回すのがポイント。速く回しすぎるとアルコール成分が急激に揮発し、香りが飛びすぎてしまう。
3.回した後、香りを確認する
⇒スワリング後、鼻をグラスの縁に近づけて香りを深く吸い込む。
【適切なスワリングの目安】
◎ 回す回数:3〜5回程度
◎ 回す時間:5〜10秒
◎ 回すスピード:ゆっくり(速すぎるとアルコールが飛びすぎる)
NGなスワリング方法
スワリングはワインの香りを引き出すための大切な動作ですが、間違った方法で行うと逆に風味を損ねてしまうことがあります。
ここでは、避けるべきNGスワリングの例を詳しく解説します。
× グラスを激しく振るように回す
⇒アルコールが急激に揮発し、香りのバランスが崩れる
⇒ワインが泡立ち、不快な舌触りになる
【影響】
ワインの繊細なアロマが失われ、アルコール臭が強調されてしまう。
特に軽めの白ワインや繊細な香りを持つワイン(ピノ・ノワールなど)では注意が必要。
× 勢いよく回して泡立たせる(スパークリングワイン)
⇒泡が消えやすくなり、炭酸の爽快感が弱くなる
⇒泡の繊細なアロマがすぐに消えてしまう
【影響】
シャンパンやスパークリングワインは、泡と香りのバランスが重要。
強くスワリングすると、せっかくの細かい泡が一気に消え、風味が弱くなる。
× スワリングしすぎる(特に熟成ワイン)
⇒長時間スワリングすると、香りのバランスが崩れる
⇒ワインが酸化しすぎて、繊細な風味が飛んでしまう
【影響】
長期熟成されたヴィンテージワインなどはすでに香りが開いているため、過度なスワリングは逆効果。
特にデリケートなワイン(ブルゴーニュの古酒など)では注意が必要。
ワインの種類別・最適なスワリングのコツ
ワインと一口にいっても、赤・白・ロゼ・スパークリングといった種類によって香りや味わいの特徴は異なるもの。
そのため、グラスを回す「スワリング」の仕方も少しずつ変えることで、より魅力を引き出すことが可能です。
| ワインの種類 | 最適なスワリング方法(目的・注意点) |
|---|---|
| 赤ワイン | ゆっくり回し、5〜10秒程度スワリング 【目的】タンニンを和らげ、香りを開かせる 【注意】速く回しすぎるとアルコールが飛びすぎる |
| 白ワイン | 3〜5秒程度スワリング 【目的】フルーティーな香りを引き出す 【注意】強く回すと酸味が際立ちすぎる場合がある |
| スパークリング ワイン | 基本的にスワリング不要 【目的】泡を長持ちさせ、繊細な香りを楽しむ 【注意】強く回すと泡が消え、炭酸の爽快感が弱くなる |
| 熟成ワイン | 1〜2回軽く回す程度に抑える 【目的】繊細な熟成香を飛ばさずに楽しむ 【注意】スワリングしすぎると香りが飛び、味がぼやける |
例えば、香りが豊かな赤ワインはしっかりと空気に触れさせるように大きめにスワリングするのが効果的。
一方で、繊細な白ワインやスパークリングワインは、泡や香りを飛ばしすぎないように、控えめで優しいスワリングが適しています。
このように、それぞれのワインの個性に合わせてスワリングの方法を工夫することで、香りや味わいをより深く楽しむことができます。
ワインに合わせて、自分にとって最適なスワリングのスタイルを取り入れてみましょう。
ワインのスワリングマナー


ワインのスワリングには香りを引き出し、味わいを深める重要な役割があります。
ぜひ取り入れていきたい技術ですが、ワインの席では「正しいマナーを守ったスワリング」が求められます。
特にレストランやワイン会などではマナーを知らずに行うと「無作法」な印象を与えることもあるため注意が必要。
最低限の教養として、ワインのスワリングに関する基本的なマナーやシーン別の適切なスワリング方法を覚えておきましょう。
基本的なスワリングのマナー
大げさにスワリングしない
【理由】
・グラスを大きく振ると周囲にワインが飛び散る可能性がある
・不必要に派手な動作は「見せびらかし」と思われることも
【適切な方法】
〇 必要以上に回しすぎない(3〜5回程度が目安)
〇 小さな円を描くように静かに回す
他の人にワインを飛ばさないようにする
【理由】
・レストランやワイン会では、隣の人の服にワインが飛ぶ危険がある
・自宅でも、テーブルや食器を汚す可能性がある
【適切な方法】
〇 初心者はテーブルに置いてスワリングするのが安心
〇 スワリングする場合も控えめに回す
スワリングするタイミングを図る
【理由】
・料理の最中や乾杯の前にスワリングすると「マナー違反」と思われることがある
・目上の人と一緒にいる場合、タイミングを誤ると失礼になることも
【適切な方法】
〇 ソムリエや主催者がワインを注いだ後、最初の一口はスワリングせずに香りを確かめる
〇 その後、ゆっくりとスワリングを行う
乾杯の前にスワリングしない
【理由】
・乾杯の前にスワリングをすると、「待てない人」「落ち着きがない人」という印象を与える
【適切な方法】
〇 乾杯の後、全員が最初の一口を味わった後にスワリングをする
香りを確認はグラスに顔を近づけすぎない
【理由】
・グラスに鼻を突っ込みすぎると「品がない」と思われることがある
・ワインの席では上品に香りを楽しむことが求められる
【適切な方法】
〇 グラスを鼻から2〜3cm離して香りを楽しむ
〇 一度に深く吸い込まず、軽く数回に分けて香る
シーン別の適切なスワリングのマナー
マナーといっても会場の雰囲気やホームパーティー、集まる人で変わります。
そこで、シーンごとに簡単にまとめてみました。
| シーン | 適切なスワリング方法 |
|---|---|
| レストラン | 静かにスワリングし、香りを楽しむ。グラスを大きく振らない。 |
| ワイン会・試飲会 | じっくり香りを確認し、軽くスワリング。必要以上に回しすぎない。 |
| カジュアルな飲み会 | 他の人にワインが飛ばないように注意し、スマートに回す。 |
| フォーマルな場 (接待など) | 目上の人がいる場合は控えめに。乾杯の前にスワリングしない。 |
スワリングは香りや味わいを引き出す大切な動作ですがTPOに応じたマナーを守ることも重要です。
正しいマナーでワインを楽しみましょう。
【まとめ】ワインの右回し・左回しは風味に影響を与えるのか?
本記事では、ワインのスワリング(グラスを回す動作)について、科学的な視点や実際のワイン愛好家の意見をもとに検証しました。
結論としてワインの右回し・左回しが風味に決定的な影響を与える科学的根拠は見つかっていません。
しかしスワリングそのものがワインの香りを引き出し、味わいを深めることは確かです。
重要なのはワインの種類やグラスの形状、スワリングの仕方です。
また、TPOに合わせたスワリングのマナーを守ることでよりスマートにワインを楽しむことができるでしょう。
宜しければこちらの記事もオススメです。




