赤玉ワインは、初心者でも楽しみやすい甘口のお酒。
ラベルは日本を連想させるデザインで、誰もが一度は見かけたことがあるのではないでしょうか。
 miku
miku実は私の初ワインも赤玉でした。
たくさんの人に愛されてきたロングセラーの赤玉ワイン。
しかし一部の方々からは「赤玉ワインはワインじゃない」と言われたり、飲み方や味について誤解されることがあります。
そこで赤玉ワインについて実際はどうなのか徹底リサーチしつつ、美味しく飲む方法をご紹介します。
赤玉ワインはただのお酒ではなく、日本のワイン文化の“入口”をつくったと言っても過言ではない存在。
この記事を通して、その魅力と楽しみ方を改めて発見してみてください。
まずは「なぜワインじゃないの?」という素朴な疑問から解き明かしていきましょう。
同じくロングセラーとして知られるアップルワインについても記事にまとめています。
歴史や味わいの違いが気になる方はぜひこちらもご覧ください。


赤玉ワインはなぜ“ワインじゃない”って言われるの?
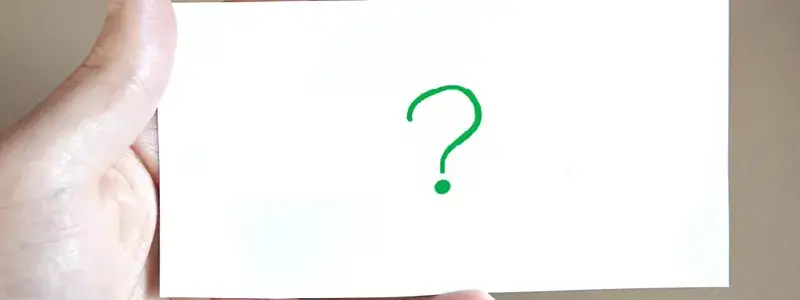
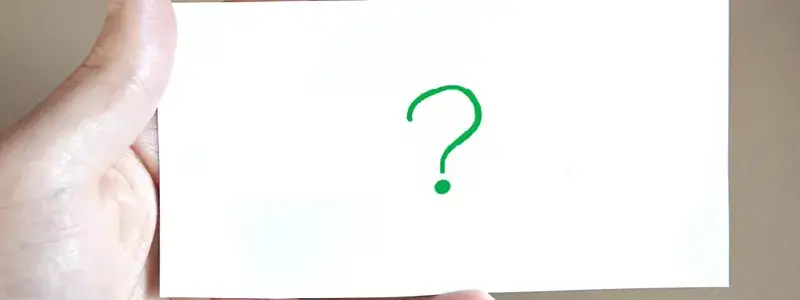
赤玉ワインについて調べると、よく出てくるのが「ワインじゃない」というフレーズです。
この疑問を解くためには、まず赤玉ワインがどういうお酒なのか、そして「ポートワイン」という名前との関係を知る必要があります。
それでは順番に見ていきましょう。
赤玉ワインってどんなお酒?100年続く歴史と特徴
結論から言えば、赤玉ワインは「ぶどうを使った甘口のお酒」で、日本では甘味果実酒というカテゴリーに位置づけられます。
つまり、国際的に定義されるワインとは少し種類が異なるのです。
なぜそのような違いがあるのか、その答えを探る手がかりは赤玉ワインの歩んできた歴史にあります。
日本人向けのワインとして甘口に
時は1907年。
当時の日本ではワインはまだ「苦い」「渋い」という印象が強く、赤玉が発売されるまで葡萄酒は漢方のような位置づけにありました。
楽しむものでもなく、庶民にはなじみの薄い存在だったんですね。
そこで寿屋(現在のサントリー)の創業者・鳥井信治郎が考案したのが、日本人に合うよう甘口に仕上げたお酒。
これがのちに「赤玉ポートワイン」と呼ばれる赤玉ワインの始まりです。
口にしたときの甘さが「ワイン=苦い漢方」という先入観をくつがえし、多くの家庭に受け入れられるきっかけとなりました。
ちなみにアルコール度数は14度で一般的なワインと特に変わりません。
製造方法が国際的なワインの定義からは外れていた
「ワイン」と認められるには、国際機関(OIV=国際ブドウ・ワイン機構など)が定める製法に則っている必要があります。
基本は「ぶどう果汁を発酵させてできたもの」で、赤玉ワインのように糖分やアルコールを後から加えると定義から外れてしまいます。
「甘味果実酒」は発酵よりも添加や調整の比重が大きいため、国際基準の「ワイン」には含まれません。
そのため日本では独自に、果実を原料としつつ甘味やアルコールを加えた酒類を「甘味果実酒」として整理しました。



杏露酒やサンザシ酒など、果実を使ったリキュール風のお酒もこのカテゴリーに入ります。
実は海外にも甘口のお酒は存在します。
フランスの「ヴァン・ドゥー・ナチュレル(VDN)」や、ポルトガルの「ポートワイン」などが代表的。
これらは「フォーティファイドワイン(酒精強化ワイン)」と呼ばれ、発酵をベースにして伝統的に造られているため、国際的に「ワイン」の一種として認められています。
「ポートワインとは?」赤玉とのつながりをチェック
ポートワインは、本来ポルトガルのポルト地方で作られる酒精強化ワインのことを指します。
これはワインの発酵途中でブランデーを加えることで、甘口でアルコール度数の高い味わいに仕上げたお酒です。
サントリー創業者はこのポートワインに出会い、「これこそ日本人に合う甘みや」と確信。
試作を重ね、スペイン産ワインをベースに工夫することで日本人に合わせた甘口の葡萄酒を完成させました。
赤玉ワインはこのポートワインを参考にして作られたため、葡萄酒ではなく「赤玉ポートワイン(西洋の酒)」として売り出されます。
赤玉ワインは「名前はワインだけど、国際的にはワインに分類されないお酒」。
製法の違いはありますが、「ポートワイン」というお酒が大きく影響しています。
独自進化を遂げた背景を見ると「ワインじゃない」と言われるのも納得できますよね。
赤玉ワインは甘くて初心者向き!ワイン入門の王道
「ワインはちょっと渋くて飲みにくい…」という声をよく耳にします。
そんな人にこそおすすめできるのが、甘口でやわらかい味わいが特徴の赤玉ワイン。
赤玉ワインはアルコールが苦手な人や、これからワインに挑戦したい人にぴったりの“入門ワイン”として長年親しまれてきました。
もちろんそのまま飲んでも良いのですが、個人的には割って楽しむほうが向いていると感じます。



そこでおすすめのアレンジ方法をご紹介していきます。
赤玉スイートワインの飲み方とおすすめアレンジ
赤玉ワインはストレートで飲むだけでなく、アレンジすることでまったく違った表情を見せてくれるお酒です。
その日の気分やシーンに合わせて飲み方を変えられるのも、赤玉ワインが初心者からベテランまで愛される理由のひとつ。
ここでは個人的に好みのアレンジや、人気のある飲み方をご紹介します。
赤玉ワインの甘さや香りを活かしながら、より幅広い楽しみ方ができますよ。
ちなみに、赤ワインを炭酸で割るときには正式な名前やアレンジ方法があります。


ソーダ割りで食事に合うさっぱりテイスト
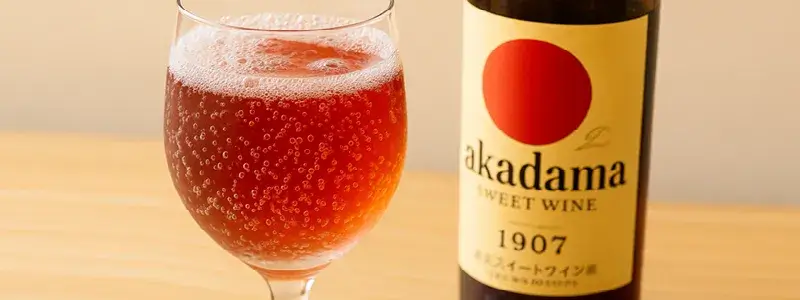
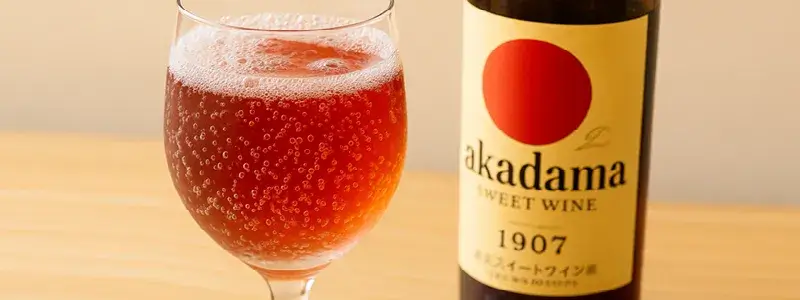
赤玉ワインを炭酸水で割ると甘さがほどよく薄まり、爽快感がアップします。
食事中にも合いやすくアルコール度数も下がるため、お酒に慣れていない人でも安心して飲めるでしょう。
レモンを少し絞って加えると、フルーティーさと爽やかさが一層引き立ちます。
フルーツを加えてサングリア風に


オレンジやリンゴ、ベリー類をカットして赤玉ワインに漬け込むと、手軽にサングリア風に楽しめます。
フルーツの甘酸っぱさがワインに溶け出し、ジュースのようにゴクゴク飲める爽やかさに早変わり。
見た目にも華やかでパーティーや女子会などにおすすめです。
バニラアイスに加えて大人のデザート


バニラアイスに赤玉ワインを少しかけると、お酒の効いた大人のデザートに。
アイスの濃厚さと赤玉ワインのフルーティーさが絶妙にマッチします。
食後の〆や特別な日のデザートにぴったりのアレンジです。
ジンジャーエール割りで爽やかな後味に


ソーダ割りに似ていますが、ジンジャーエールで割るとスパイシーさが加わってより爽快な味わいに。
暑い夏の季節にはぴったりの一品で、簡単にバーのカクテル気分を味わえます。
赤玉ワインが甘いため、特にキリっとしている辛口のジンジャエールがおすすめです。
意外にも合うカルピス割り


赤玉ワインはソーダやフルーツとよく合いますが、実はカルピスで割っても美味しく楽しめます。
濃厚な甘さの赤玉にカルピスの酸味とまろやかさが加わり、意外にも爽やかな後味に。
甘すぎるのが苦手な人でも飲みやすく、夏にぴったりのアレンジとしておすすめです。
寒い季節におすすめ!赤玉ホットワイン


冬にはホットワイン風のアレンジもおすすめです。
耐熱グラスに赤玉ワインを注ぎ、電子レンジで軽く温めるだけ。
シナモンやスライスオレンジを加えると、本格的なホットワインのような味わいに。
体も温まり、甘さと香りが一層広がります。
ちなみに赤玉ワインのように“飲みやすさ”で人気を集める本格派の日本ワインもあるんです。
ご興味のある方はぜひチェックしてください。


赤玉ポートワインは体に悪い…?徹底リサーチの結果


赤玉ワインを調べていると「体に悪い」という言葉を見かけることがありますが、本当なのか気になりますよね。
結論から言えば現在販売されている赤玉ワインは、酒税法や食品衛生法に基づいて造られた一般的なお酒です。
普通のアルコール飲料として安心して楽しめます。



問題があればロングセラーではなく販売中止のはずですからね。
ではその噂がどこから生まれたのか、そして実際にどんな原材料や添加物が使われているのか整理していきます。
赤玉ワインの原材料とその特徴
まず、赤玉ワインの原材料を確認してみましょう。
出典:サントリー公式
基本となるのは「ぶどう果汁」、そこに輸入ワインや酸味料を加えて仕上げています。
また、ぶどう果汁の香りや風味を引き出すために香料を加えることもありますが、特別なものではありません。
赤玉ワインの味わいが「ジュースみたいで飲みやすい」と言われるのは、この材料構成によるものです。
添加物も広く一般的なもののみ
「体に悪い」と言われる理由の一つに「添加物」があります。
しかし、赤玉ワインに使われている添加物はワインやリキュール、清涼飲料などにも広く利用されている一般的なものです。
たとえば酸化防止剤(亜硫酸塩)はワイン全般に使われるもので、味や香りを守るために欠かせません。
これは国際的にも認められた添加物で、基準値内で使用されている限り悪影響はほどんどないとされています。
ごく一部の方はアレルギーのように過剰反応があるようですが、それはどの食品や飲料にも言えます。
糖分添加も「甘さを調整するため」に加えられますが、これはジュースや缶チューハイと同じ感覚で差し支えありません。
つまり、赤玉ワインに含まれる添加物は「特別な危険があるもの」ではなく、安心して楽しめる範囲です。
赤玉ポートワイン事件とは?名張毒ぶどう酒事件との混同
赤玉ポートワイン事件で調べると1961年に三重県名張市で発生した「名張毒ぶどう酒事件」がヒットします。
しかし、名張毒ぶどう酒事件で提供されたお酒の銘柄は公式に明らかにされていません。
また、赤玉との関連情報もヒットしません。
つまり「葡萄酒」や「果実酒」というワードから、当時広く流通していた「赤玉ポートワイン」に焦点が充てられている可能性が高いです。



つまり「赤玉が関係していたのでは」という推測や誤解によるものと考えられます。
「赤玉ポートワイン事件」は確認できず、被害なども特に見当たらなかったので安心してください。
赤玉ワインはどこに売ってる?ベストな入手方法


結論からいうと赤玉ワインはスーパーや酒屋でも見つけることができますが、必ず置いてあるとは限りません。
そのため確実に手に入れたいならオンラインショップを利用するのがベスト。
実際、最近は昔よりも見かける機会が少なくなったように感じています。
ここでは赤玉ワインを探すときに役立つ入手ルートを整理してみました。
近所のスーパーで買えるかも!赤玉ワインの取り扱い事情
まず、もっとも身近な入手先はスーパーや酒屋です。
赤玉ワインはロングセラー商品のため、今でも店頭で取扱っているところがあります。
特に大きめのスーパーや、品揃えの豊富な酒屋で見つけやすいでしょう。
ただし、小規模なスーパーや地方の店舗では置いていないこともあります。
もし近くのスーパーに赤玉ワインがない場合は、店員さんに取り寄せをお願いできるか聞いてみてもいいでしょう。
地域の流通状況によって在庫に差があるため、事前に確認しておくと安心です。
確実に入手ならオンラインストアがベスト
確実に手に入るのはオンラインショップです。
Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなど大手通販サイトでは、常に赤玉ワインが出品されています。
オンラインで買うメリットは「確実に在庫があること」と「自宅に届く便利さ」。
特に地方に住んでいて近くに酒屋が少ない人にとっては、とても頼れる入手先です。
また、通販サイトではギフト用の包装やセット販売も選べるので、贈り物として利用したいときにも便利。
さらに、価格を比較して安く買えるのもオンラインの強みです。
セールやポイント還元を利用すれば、店頭よりお得に手に入ることもありますよ。
赤玉ワインには“白”がある!?
赤玉ワインは「赤」が一般的に知られていますが、実は 「白(ホワイトタイプ)」もあります。
サントリー公式にも「花のようにやさしい香りと自然な甘さをお楽しみ下さい」と紹介されています。
色だけでなく味わいにも違いがあり、白タイプは ぶどう品種にナイアガラ種を使用しているため、スパイシーさとやさしい甘さが特徴。
こちらはメジャーな赤玉に比べると店頭に置いてあることが圧倒的に少ないです。
オンラインストアには取扱いがあるので、気になる方は入手してみてください。
「赤玉は赤だけ」と思っていた人にとって、白タイプはびっくりするはず。
どちらも違った魅力があるので、「香り重視なら白」「ぶどう感を楽しみたいなら赤」と使い分けるのもおすすめですよ。
赤玉ワインは飲みやすい分、ついグラスが進んでしまうことも。
そんなときに気になる“適量”についてはこちらで解説しています。


赤玉ポートワインと赤玉スイートワインに違いはない
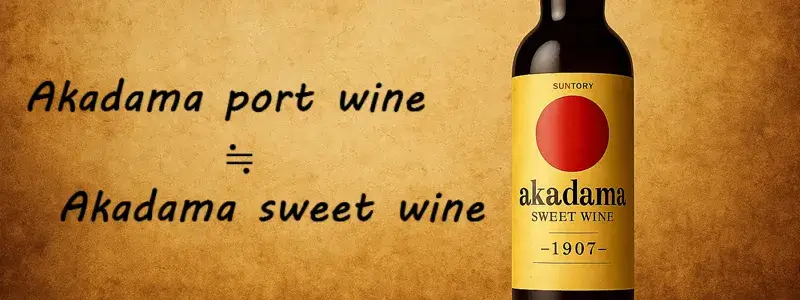
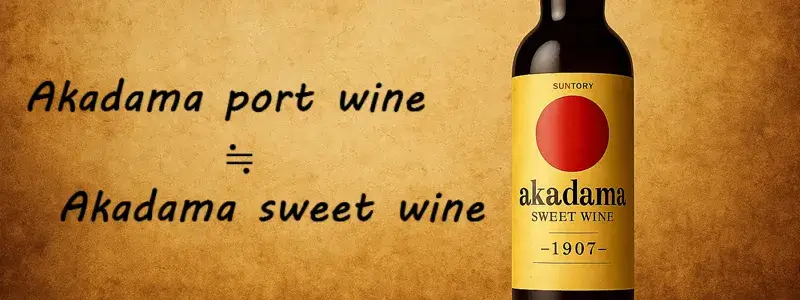
赤玉ワインには「赤玉ポートワイン」と「赤玉スイートワイン」という2つの名前があります。
一見すると別の商品に思えますが、実際には中身が大きく変わったわけではなく、同じお酒が時代とともに呼び方を変えただけです。
出典:サントリー公式
つまり「ポートワイン」と「スイートワイン」に本質的な違いはありません。
ではなぜ名前が変わったのか、その背景について詳しく見ていきましょう。
赤玉スイートワインと呼ばれるようになったのは1973年
赤玉ワインが誕生して数年後、原産地呼称を守るマドリッド協定が結ばれました。
これはワインのシャンパンやボルドーなどの呼称と同じ考え方です。
協定により国際的に「ポートワイン」という名称はポルトガルの特定地域で造られたワインだけに使用と定められたのが1973年。
このルールに対応するため、「赤玉ポートワイン」は「赤玉スイートワイン」という名前に変更されました。
この変更はあくまで国際基準に合わせたものであり、味や品質が大きく変わったわけではありません。
むしろ「スイートワイン」という新しい名前は、その甘さと親しみやすさをわかりやすく表現するものとなりました。
赤玉パンチは“幻”じゃない!今でも楽しめるソーダ割りタイプ
赤玉ワインの派生商品として、今も販売されているのが「赤玉パンチ」です。
赤玉スイートワインをベースに、ソーダやレモンの爽やかさを加えたワインサワーで、軽やかで飲みやすいのが特徴的。
赤玉パンチは缶や紙パック、濃縮コンクタイプなど複数の形で販売されており、スーパーやオンラインストアで入手できます。
「販売終了したのでは?」と噂されることもありますが、それは一時期市場から姿を消した時期があったことや、地域による取扱いの差が原因と考えられます。
実際には現在も製造・販売が続いており、若い世代にも「軽く飲める甘口サワー」として人気の商品。
「ワインは苦手だけど赤玉パンチなら飲める」という声もあり、ワインを気軽に楽しむ入口として支持されています。
【まとめ】赤玉ワインは“ワインじゃない”けど、やっぱり愛されている
ここまで赤玉ワインについて詳しく見てきました。
赤玉ワインは確かに「ワインじゃない」ですが、それは分類上の話にすぎません。
ワインじゃなくても愛され続けてきた歴史があるならそれでいいと感じています。
改めて今回の内容を整理してみましょう。
【赤玉ワインまとめ】
・赤玉ワインは「甘味果実酒」に分類されるため“ワインじゃない”と呼ばれる
・ポートワインを参考に日本人向けに造られた、初心者でも楽しめるお酒
・そのまま飲むのもいいが、アレンジするのがおすすめ
・「体に悪い」という噂は誤解、安心して飲める
・スーパーや酒屋でも買えるが、確実に入手するならオンラインがベスト
・「赤玉ポートワイン」は、1973年に「赤玉スイートワイン」に改称された
・赤玉ポートワインと赤玉スイートワインは同じ商品
・赤玉が有名だが、実は「白」もある
・派生商品の「赤玉パンチ」は現役で販売中
赤玉ワインは、ただの「古いお酒」ではありません。
100年以上前から人々の食卓を彩り、今もなお新しい世代に愛され続けている“日本の甘口ワイン文化の入り口”です。
「ワインはちょっと難しそう…」と思っていた人も、赤玉ワインならきっと笑顔になれるはず。
あなたの家のテーブルに並んだ瞬間からちょっと特別で、ちょっとレトロで、そしてとびきり楽しい時間が始まります。
ぜひ、次の一杯に“赤玉”を選んでみませんか?
宜しければこちらもご拝読ください。





